「アブソリュート・チェアーズ」(埼玉県立近代美術館)レポート。ウォーホルやベーコン、名和晃平らの作品を通じて「椅子の絶対的魅力」に迫る
ミシェル・ドゥ・ブロワン 樹状細胞 2024
国内外の28組による83作品を紹介
アートにおける「椅子」の表現に着目した展覧会「アブソリュート・チェアーズ」が2月17日、埼玉県立近代美術館で開幕した。会期は5月12日まで。その後、愛知県美術館に巡回する(会期:7月18日~9月23日)。
1982年の開館当初から優れたデザインの椅子を収集し、常時数種類を館内に設置している埼玉県立近代美術館。「椅子の美術館」としても親しまれる同館が、満を持して愛知県美術館と共同企画したのが本展だ。プレス内覧会で建畠晢・埼玉県立近代美術館館長は、「様々なアーティストを魅了してきた椅子の絶対的(アブソリュート)な魅力について考察した」と話した。

展覧会は、戦後から現代までの国内外の28組のアーティストによる83点を紹介。作品の手法は立体、映像、インスタレーションと様々だ。企画グループメンバーの佐伯綾希・同館学芸員は本展についてこう説明する。
「従来のデザイン展と視点を変え、アートの視点から椅子という存在に迫った。生活のあらゆる場面で用いられている椅子は人間や社会と密接な関わりを持ち、そのなかで幅広い意味を纏っている。美術家は各々、椅子の持つ意味をとらえて作品に反映してきた。美術作品における椅子の在り方の中に私たちの社会や文化を見つめ直す手がかりが詰まっているのではないか」

海外作家が滞在制作した新作
館内に入るとまず目につくのは、副産物産店が作品輸送用のクレートや木製パレットを再利用して作ったベンチ。副産物産店は山田毅と谷津吉隆による資源循環プロジェクトで、アーティストのスタジオから出る廃材を使い、加工・編集して作品を制作する。会場でも本展のために2人が作り上げたユニークな椅子があちこちに置かれ、来場者は自由に腰かけることができる。
センターホールの吹き抜けには、トゲだらけの奇妙な球形が宙に浮かんでいる。カナダ出身のミシェル・ドゥ・ブロワンが、約40脚の会議用椅子を使い滞在制作した新作《樹状細胞》。本作を担当した松江李穂学芸員によると、1970年生まれのドゥ・ブロワンは、既製品を用いて産業・経済システムや様々な力学を可視化する彫刻・映像作品やインスタレーションを手がけ、日本での展示は今回が初めて。
内覧会に出席したドゥ・ブロワンは、本作は2005年に発表した作品を発展させ、人体の表面を覆う免疫細胞の一種からインスピレーションを得たと説明。「コミュニティの象徴である椅子が等間隔に並び、外部に対し閉じた球体の形状は、人間の集団が取る防御的姿勢や集団免疫を想起させるかもしれない」と話した。

コンセプチュアルな草間、岡本作品
2階展示室で行われる本展は5章構成。第1章「美術館の座れない椅子」は、冒頭にありふれた木のスツールに車輪を固定したマルセル・デュシャンの《自転車の車輪》を展示。既製品をアートに転用した、初めての「レディメイド」作品だ。

草間彌生の柔らかい突起物で覆われた椅子型オブジェ、岡本太郎《坐ることを拒否する椅子》、高松次郎の《複合体(椅子とレンガ)》も並ぶ。いずれも椅子本来の機能を脱臼させ、鑑賞者にコンセプチュアルな問いを投げかける。切断した椅子をカラフルに塗り、即興的に組み立てたジム・ランビーの作品は、芸術と日常を接続する素材として使われている。


第2章「身体をなぞる椅子」は、人間の体を受け止める身体性に注目。フランシス・ベーコンによる肢体が溶け落ちるような絵画、肥大化した2つの脳がキスを交わす工藤哲巳のアイロニカルな彫刻が目を引く。「ともに戦争の悲惨なイメージから派生した崩れゆく身体を支えるものとして椅子を扱っている。両作家の椅子のとらえ方が似通っていることは、今回の大きな発見だった」と佐伯学芸員。
ときに椅子は身体を補助する機能を持つ。アンナ・ハルプリンの《シニアズ・ロッキング》は、当時85歳だった作家が身動きが不自由な高齢者にダンスを振り付け、座ったまま踊る様子を映像に収めた。ロッキングチェアをリズミカルに揺らし、手を振り上げる姿は生気にあふれている。

権力を象徴する玉座、電気椅子
玉座のように権威を象徴したり、電気椅子のごとく死を目的に使われたり。第3章「権力を可視化する椅子」は、アンディ・ウォーホルのシルクスクリーン連作「電気椅子」をはじめ、死や暴力、強いられる規範に対し椅子が象徴的に登場する作品を紹介。中国出身のシャオ・イーノン&ムゥ・チェンによる文化革命期の集会場の写真連作、ビデオアートの先駆者ダラ・バーンバウムが「座らされた」自身を観測した映像作品、渡辺眸が1960年代後半の東大全共闘を撮影した写真などが並ぶ。渡辺作品は、学生たちが教室の椅子が大量に使ってバリケードを築いた場面が写され、大学の秩序崩壊を伝える。

1975年の独立後、20年近く内戦が続いたアフリカのモザンビーク。クリストヴァオ・カニャヴァート(ケスター)の《肘掛け椅子》は、内戦で使用されたソ連製銃器などを解体し、部材を再溶接して作られた。戦争終結後に残った大量の武器を農具などに変える「銃を鋤に」プロジェクトの一環として制作したもので、国際的な武器市場の存在や地政学的な問題も考えさせる。

拷問器具を連想したのは、ポーランド出身のミロスワフ・バウカによる《φ51x4, 85x43x49》。斜めに宙づりにされた椅子と、その足元に置かれた鉄輪で構成されている。鉄輪が埋もれている白い塩は、迫害と圧政に苦しめられた人々の涙が結晶したようだ。

日常の様々な場面で目にする椅子は、記憶や個人的な物語、多様なイメージが宿る存在でもある。第4章「物語る椅子」は、気化するナフタリンを使い歴史と記憶を表現する宮永愛子、無数の透明な球体で表面が覆われた「PixCell」シリーズで知られる名和晃平、ベルギー出身のハンス・オプ・デ・ビークの彫刻が一室にゆったりと配置され、本展の大きな見どころになっている。


ソファに横たわり、まどろみ続ける少女。オプ・デ・ビークの《眠る少女》は、灰色一色に塗り込めた色彩が、時間が静止したような感覚をもたらす。夢見るような少女の顔や体に掛けられた毛布に記憶を揺さぶられる人も多いだろう。
第4章は、様々な状況の椅子が写り込んだ潮田登久子の写真連作「マイハズバンド」や、石田尚志によるイメージと実体が交錯するドローイング・アニメーション作品も紹介。刺繍で日用品の輪郭を再現するYU SORAのドローイングは、黒い糸が所々で切れて下がり、日常の儚さを暗示する。
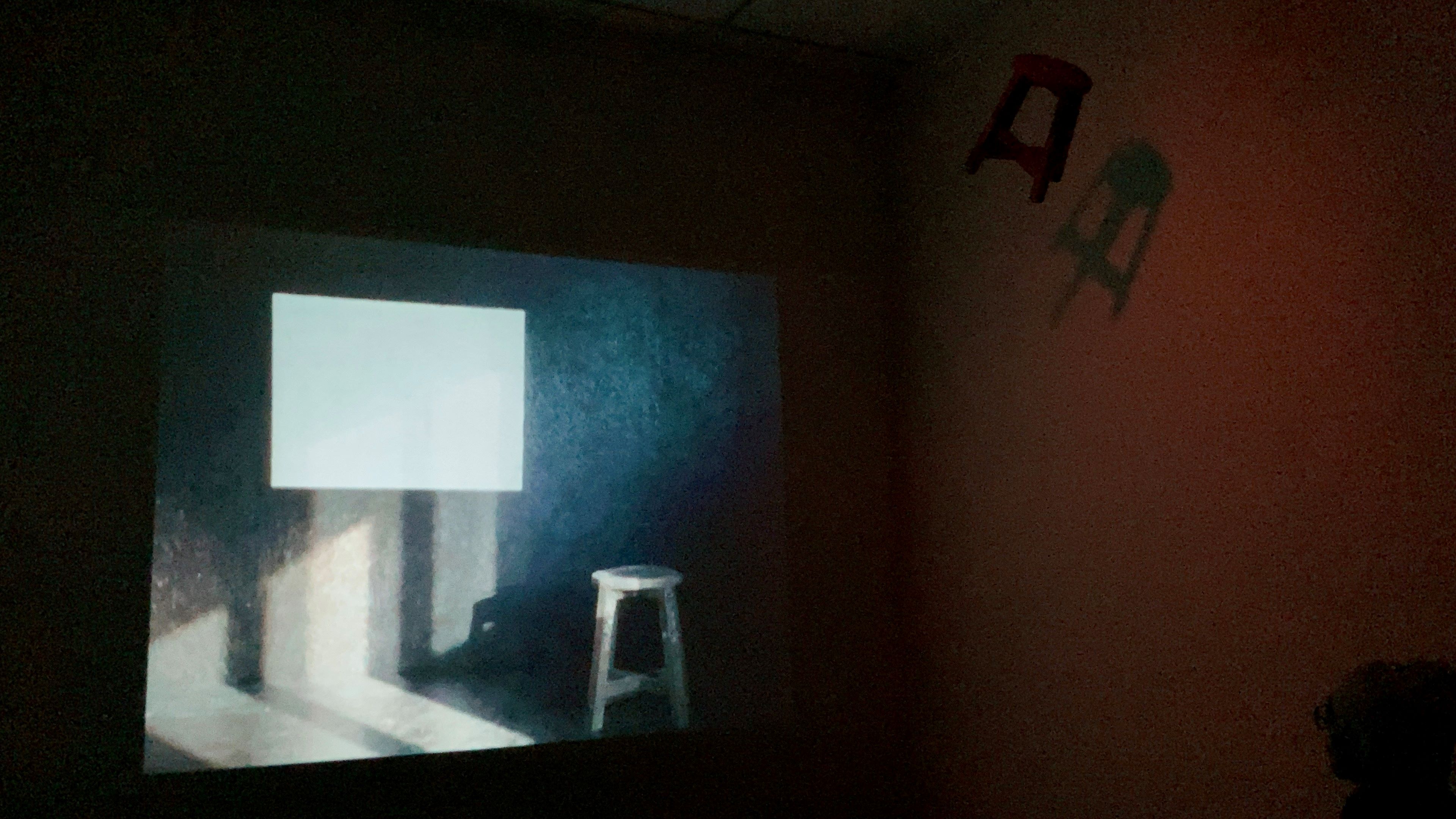

「排除アート」をモチーフに
第5章「関係をつくる椅子」は、椅子が結ぶ関係性に焦点を当てる。チェスセットがある机を挟み2脚が向き合うオノ・ヨーコの作品は、駒や盤も真っ白に塗られている。対戦する際は、相手を信頼しお互いの記憶をたどってプレイする必要があり、作家のユートピア的な理想がうかがえる。

本展のために制作された檜皮一彦の映像作品は、車椅子ユーザーがいる状況での避難訓練のプロセスを記録した。道路の段差など困難がある車椅子の移動を通じ、参加者がコミュニケーションを深めていく様子が伝わる。檜皮は「災害避難所に指定されている美術館は多いが、館内は規制が多く、実際に避難するときの制度的な問題も感じた」と話した。

友好関係に役立つ椅子だが、一定の人間を排除するかたちに作られることもある。たとえば、公共のベンチに仕切りを設け、横たわれないようにした「排除アート」。シンガポールを拠点に活動するダイアナ・ラヒムは、そうした排他的な構造物を調査し、親密感を演出する装飾を加える活動を行う。タイ出身のスッティー・クッナーウィチャーヤノンのインスタレーションは、母国の通俗的なイメージを覆すようなモチーフが椅子に刻まれている。


アート作品を通じ、日常的な椅子に含まれる含意を読み解く楽しみを与えてくれる本展。多様な文化や社会背景も伝える展示は、ほとんどが日本にある作品で構成され、国内コレクションを活用した好企画と言える。なお、館内には実際に座れる名作椅子が複数あるので、そのデザインの妙や快適さもぜひ味わいたい。



