広島市現代美術館「リニューアルオープン記念特別展 Before/After」レポート。シリン・ネシャット、石内都、田中功起ら45組の作品が集う本展の見どころを徹底解説!
展示室A-2 田中功起《everything is everything》(2005-06)
現代美術の重要拠点がリニューアル
1989年5月に開館した広島市現代美術館。いまでは現代美術を扱う美術館は国内に複数あるが、公立美術館で初めて本格的に現代美術に取り組んだのが、じつは本館だった。30年ほどの活動を経て、2020年12月より改修工事のため休館。施設・設備の機能「回復」と「拡張」が行われた。そしてこの3月18日、約2年3ヶ月ぶりにリニューアルオープンした。

この休館期間はほぼコロナ禍と重なる。3月13日には厚生労働省が「マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本」との方針を示し、19日には広島市で桜が開花。市街地には海外からの観光客も多く見られた。移動の制限や様々な活動の小休止を経て、春の暖かな日差しとともに開放感が街に広がりつつある。今回のリニューアルオープンは、そんな晴れやかな雰囲気のなかで行われた。
Tokyo Art Beatは、17日に行われた内覧会を取材。「リニューアル記念特別展 Before/After」を企画担当した同館学芸員・角奈緒子のインタビューを交えながら、新しくなった美術館と本展の見どころを紹介したい。
「リニューアル記念特別展 Before/After」

「Before/After」は、改修工事を経ることで生じる美術館の「前/後」を起点に、様々な事象の「まえ」と「あと」をテーマに据えた企画展だ。広島の歴史や人間の尺度を超えた時間までを視野に入れ、コレクションを軸に、45組の作品を展示する。現代美術館の宝というべき著名作家の作品をはじめ、9名のアーティストが今回のために新作を発表。広島と縁のある石内都の新作が見られることも嬉しいが、90年代生まれの気鋭のアーティストも積極的に起用され、世界の「いま」を照らそうとする美術館の熱い意気込みが感じられる。
また同館16年ぶりの新規購入作品となったシリン・ネシャットの《Land of Dreams》(2019)もハイライトのひとつ。作家は2005年に第6回ヒロシマ賞を受賞している。
改修工事で何が変わったのか

建築家・黒川紀章が設計した同館は小高い比治山公園の上に位置し、自然の景観との調和が意識されている。
今回の改修では建築の意匠を大切にしながら、防・排水設備の補修や、照明のLED化といった展示室の機能更新に加え、展示室内のエレベーター増設など、バリアフリー向上のための機能拡張が行われた。またベビーケアルーム(授乳室)や、だれでも・多目的トイレ、キッズスペースも新設されている。


またエントランス横には空間が増築され、ガラス張りの開放的なカフェと、ワークショップなど様々な用途に活用できる多目的スペース「モカモカ」が誕生した。
「Before/After」展は、改修工事の完了した建物も展示の一部として位置づける。最初の展示室A-1には工事の図面や記録写真、動画などの資料や、役目を終えた器具や部品など、工事現場から救いあげられたものたちが並び、工事の「まえ」と「あと」の建物の様子が紹介される。

「Before/After」というテーマは、もともとこの建築が持っていた、大きな時間の流れや変化への志向を受け継いでいる。ここで、黒川紀章による建築の特徴を振り返っておきたい。
まずは素材。建物は、下から上へいくにしたがって自然石、タイル、アルミ……と人工的なものに素材が変化するようになっており、過去から未来へ至る文明の発展や時間の流れが表現されている。
また、文化の融合も目指された。たとえば江戸の蔵をイメージさせる切妻屋根、古代ヨーロッパを思わせる円形の広場など、様々な要素が組み合わされている。
過去・現代・未来をつなぐ意匠が随所に凝らされた同館は、リニューアルによってそのメッセージをさらに明確にしながら、新たな一歩を踏み出したと言えるだろう。

サインに注目。固定的なジェンダー・イメージに囚われないピクトグラムも
館内サインにも注目したい。過去に使われていたサインはどれもわかりやすく公立美術館らしい雰囲気だが、ちょっと時代も感じさせる。
そこで、リニューアルではサインも一新。黒川紀章建築都市設計事務所が監修した。ピクトグラムは本館の建築意匠からかたちを引用し、組み合わせて作成されたという。特筆したいのは、現代的なジェンダー視点や多様性への配慮が盛り込まれていること。館内に掲示された「どちらに入ればいいか 迷っている方々へ」という看板には以下の説明がある。

「女性/男性を表すピクトグラムを作るにあたり、それぞれの性に割り振られてきた特徴にできるだけ頼らないように務めました。そのため、従来のピクトと比べて、分かりにくく感じられるかもしれません。ですが、むしろこうした分かりにくさを受け入れていくことで、私たちは様々な窮屈さから自由になっていけるのではないでしょうか。当館は多様な人が安心できる場所となることを目指しています。」
また、来館者はまず、コインロッカーやチケットカウンター、カフェなどに、様々なかたちの楽しげなタイポグラフィー(文字デザイン)を見つけることになるはずだ。一般的には、こうしたところの書体は揃えるのがセオリー。しかし同館は「新生タイポ・プロジェクト」として書体デザイナーの岡澤慶秀、グラフィック・デザイナー岡本健+を迎え、リニューアルで変貌を遂げた箇所などのために、それぞれ異なる文字で表示を作成した。


これらの文字は、美術館の近隣地域や館内、館にまつわる資料などからタイポを調査し、それらの特徴を生かして作られている。タイポを再活用する実験的なこの試みは、「Before/After」というテーマのもと、同館の変わったところと変わらないところをともに示して見せる。

劣化するモノ/作品を収蔵するという美術館の宿命
本展は、展示テーマの伝え方もユニークだ。いわゆる章立ては行わず、館内の壁などに「#(ハッシュタグ)」を使って、近隣の作品に関するキーワードを複数提示する。
前述の改修工事にまつわる展示室と、デニス・オッペンハイムによる日焼けの前と後の写真を組み合わせた象徴的な作品のあいだには「#変化」「#更新」「#物質」「#劣化」「#アーカイブ」というハッシュタグが。これらの言葉が、前室と次の田中功起《everything is everything》がある展示室A-2とをゆるやかにつなぐ。

2006年に台湾で発表された本作は、現地で購入された日用品の新たな用途を探る様子を撮影した映像と、実際に使用された日用品とで構成されている。角学芸員は、本作についてこのように語る。
「様々なものごとの『前/後』を想起させてくれる作品や作家と一緒に展覧会を作りたいと考えたとき、ひとつのきっかけとなったのが、当館が所蔵する田中さんの《everything is everything》でした。作品で使われている日用品はプラスチックなどでできているので、どんどん劣化して壊れていくことがわかっている。それらをどのように保持したり交換したりしながら持ち続けていくのか、そうしたことを作家と一緒に考えたいと思いました。その実践の様子も合わせて展示しています。
変化していくものをどう留めていくかは、美術館にとって避けられない普遍的な問題です。そうした変化、変質、変容という視点から、ほかの作品も選んでいきました」。
階段をくだり、地下の展示室A-3へ移ろう。半円形が印象的なこの空間に入ると、ほぼ中央にある若林奮の大きな彫刻《DOME》(1988)が目を引く。そしてそれを取り囲むように、若手・中堅アーティストたちの新作が並ぶ。
竹村京の「修復」シリーズも、変化や変容について示唆に富む作品だ。壊れた陶器や家具などの破損部分を絹糸で縫い直したり、刺繍を施した布を写真やドローイングの上に重ねたりすることで生み出される。絹糸には、クラゲに由来する蛍光成分が含まれており、ブルーライトを当てることで発光している。

「たとえばお皿が割れてしまったら、普通は捨てることが多いですよね。しかし彼女はそれらを優しくくるんで、刺繍を施すことで別のものに変容させます。日用品としての寿命が終わってしまっても、そこには持っていた人の記憶が含まれていて思い出がある。そうした時間の経過も組み込まれた作品です。同じく日用品を扱っていても、田中さんの作品と竹村さんの作品ではアプローチが異なりますし、その多様なあり方を本展で感じていただけたら嬉しいです」(角)。
新作に使われたのは、もともと美術館の改修工事を進めるなかで壊れてしまった回廊のガラスや、学芸員の私物だったものたちも含まれていると言う。竹村によれば、この絹糸の美しい蛍光色は長くは保たず、ブルーライトに当たることで薄れていくそうだ。本展の期間中にも、新たな糸で縫い合わせるなどメンテナンスが必要になりそうだという。様々なものが持つ固有の時間と、絶え間ない変化・修復という営みについて考えさせられる。
髙橋銑は彫刻の保存修復に仕事として従事しながら、作家として作品を制作。出品されている「Cast and Rot」はその代表的なシリーズだ。

「干からびた人参に、ブロンズ彫刻に用いられる保存処置を施すことで作られた作品です。もはやブロンズ彫刻なのか人参なのかわからない、そっくりなものができあがりました。修復家として作品の修復に携わるなかで、髙橋さんはそうした修復が作品にとって本当に正しいあり方なのか、未来永劫に残っていくとはどのようなことなのか、ひいては人が生まれてから死ぬまでと、ブロンズ彫刻が作られて朽ちていくことについて、思いを馳せるようになったといいます。
ブロンズに見えるけれどブロンズではない人参たちが、いろんなポーズで展示されている。これらはいつまで保つのだろうか、ブロンズのように変化しないのだろうかということをささやかに問うています。それはブロンズという確立された彫刻の素材に対しても疑問を向ける彫刻です」(角)。
解放された新しい彫刻たち
本展最年少のコウミユキは広島市立大学大学院で学んだ。床に配置された数多くの犬の置物は、何かが合成されたキメラ的な出立ちだ。
「コウミユキさんは、庭などに置いてある陶器の犬の置物がオスワリのポーズをとっていることが多いとあるとき気づきました。その従順な姿を見て、解放してあげたいと思ったんですね。それで後ろ足の部分を叩き割り、部分的に破壊してから組み立て直す「Stand Up!」というシリーズを展開しています。立たせてあげることで犬たちを解放し、別の生き方や道を与えるような本作は、作家にとっても自分の姿を重ね合わせて頑張ろうと思える作品なんだそうです。作家の手にかかれば犬の置物が立ち上がる、このこともBefore/Afterを表すものだと解釈しました」(角)。
平田尚也は美術家・彫刻家だが、その彫刻はヴァーチャル空間内に存在するというユニークな手法を採る。本展でも、鑑賞者がゴーグルを着用しVR空間にダイブ、そこで様々な彫刻作品と出会う《Sweet heaven explorer》(2023)を発表する。
最初は展示空間らしい、小さな部屋に分かれた場所でいくつかの彫刻を見るのだが、ある場所から空の上へと移動すると、そこには先ほど見た彫刻が、巨大な建物サイズになって空に浮かんでいる。鑑賞者はそこに登ったりすることができるので、自分の身体と彫刻作品を、平常時とは異なるスケールで味わうことができる。(*VR を利用した鑑賞は事前予約が必要。空きがある場合に限り、当日会場でも申込可。詳細はこちら)
「若林奮さんの鉄によるマッスとしての彫刻と、ヴァーチャル空間で展開される、実態を伴なわない非常に軽やかに感じられる平田さんの彫刻。ここには『彫刻』という概念におけるかつて(=まえ)といま(=あと)の対比も感じてもらえると思います」(角)。

同フロアの展示室A-4では、新収蔵品となるシリン・ネシャットの大規模なインスタレーション《Land of Dreams》を初披露。ニューヨークを活動拠点とするイラン人アーティストで、現代イスラム社会を生きる女性たちの抑圧された状況や、イランのみならず政治的・社会的な問題を扱ってきた。《Land of Dreams》はアメリカのニューメキシコ州で撮影された夢と現実をテーマにしたふたつの映像と、地元住民を撮影した複数の写真で構成されている。
歴史と時間の尺度を考える
続いて、回廊を渡り別棟の展示室Bへ向かおう。
大きなガラス窓が気持ちのいい回廊では、田村友一郎の作品を展示。特定の場所の歴史や文脈を探求し、そして掘り下げて作品を制作することで知られるアーティストだが、今回はもちろんこの美術館が舞台だ。《ずるい彼》は田村が2019年の同館30周年記念展に際して制作した作品で、同館開館日である1989年5月3日に撮影された、公衆電話で話す女性たちが写った写真が起点になっている。

この写真の女性たちが使っていた公衆電話は時代とともに撤去され、今回の改修によって電話ブースは展示スペースに生まれ変わった。大きなガラスが手前に設置され、その後ろの蛇紋石でできたブース部分を生かし、作品が展示できるようになった。田村はここに新作《ガラスの花嫁》を展示。電話ブース(Before)と展示スペース(After)、《ずるい彼》(Before)と《ガラスの花嫁》(After)という二重の「Before/After」だ。
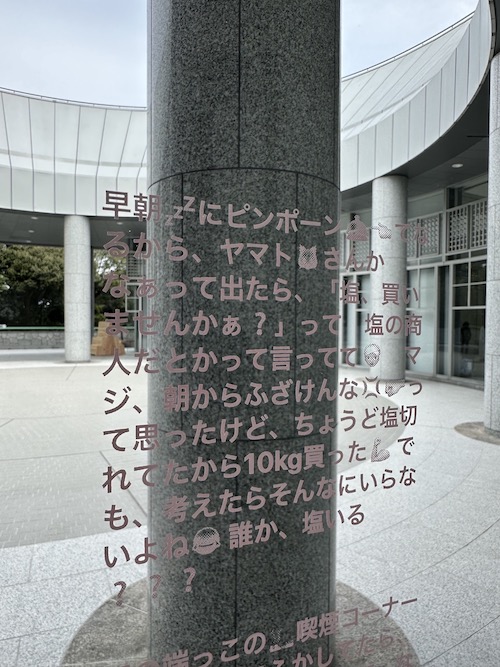
「《ずるい彼》の一部として回廊の窓に書かれた言葉は、田村さんが想像した、開館日の電話ブースにいた女性のひとりと電話をかけている相手(男性)との会話です。その内容は、開館同日にテレビで放送された音楽番組「夜のヒットスタジオ」で少年隊が歌った「デカメロン伝説」と工藤静香「嵐の素顔」の歌詞がもとになっています。
時は流れ、公衆電話に代わって人々はスマホを駆使するようになりました。新作《ガラスの花嫁》で田村さんが展開するストーリーは、あるキャバ嬢と友人とのLINE風チャットの会話です。でも、なぜキャバ嬢なのか。それは本展が「Before/After」だからです。Afterをアフター(⤴)と語尾をあげて発音する用語から、田村さんはキャバ嬢を連想しました。楽しい連想ゲームは多方向に広がり、展示ブースの前に設置された大きなガラスから、デュシャンの通称「大ガラス」(《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》)へ、さらに工藤静香さんから娘のKōki,さんとCocomiさんへ……。こうして想像&創造されたのが《ガラスの花嫁》なんです」(角)。
展示室B-1は横山奈美の絵画からスタート。壁には「#歴史」「#忘却」「#わたし」「#planetary」「#人間尺度を超えて」といったハッシュタグが見える。
横山の「Shape of Your Words」シリーズは、ある単語を様々な人に書いてもらい、それをネオン管で再現した状態を油彩画で描いたシリーズ。本展では、「history」の様々な手書き文字を描いた新作を発表する。

「横山さんに展示の相談をした際に、historyという言葉で新作を考えていると聞いて、本展にぴったりだと思いました。歴史というのはまさに前/後の連続で成り立っているものですから。そのうえで重要なのは、たったひとつの歴史ではなくて、たくさんの人による歴史が集まっているということ。大きい体制や国家という声が強いものによって歴史が編纂され残っていくことが多いわけですが、言葉のポートレイトである本作は、作家にとって身近な人が書いた文字を絵画にしています。それぞれにとってhistoryとはなんなのかを考えさせられます。
よく見るとネオン菅の文字よりも、じつは背景のほうがずっと精巧に描かれていることにも注目してほしいです。光り輝くものだけではなく、それを支えているものがあるという作家の着眼点は素晴らしいメッセージだと思います」(角)。

横山の「history」と向き合うように展示されているのは、河原温の代表作「Today」シリーズだ。その日の日付をキャンバスに描き、当日中に描き終らない場合は破棄するというルールを自らに課した本シリーズは、作家の生存の証として1966年から生涯に渡って続けられたもの。
様々な人々が描いた「history」という大きな時間の流れと、たったひとりの個人が描いたある特定の日付。イメージの喚起力に溢れた、見事な対比だ。現代美術を代表する著名作家と若手作家をあえて対峙させるという企図が冴える。
ヒロシマの景色と出会う
ヤノベケンジや森村泰昌らの作品に続き、広島県生まれでドイツ在住の和田礼治郎の作品が並ぶ。
「和田さんは自然に切り込んでいくような大きな彫刻を制作してきましたが、近年はワインなどの液体で満たされた彫刻を発表しています。西洋の文化においてワインはキリストの血を象徴するもので、そこから様々なことを想起させます。広島出身であることを思えば、血や赤といったイメージは戦争や原爆の記憶ともつながるでしょう。
現在の広島の風景を、ワインのフィルターを通して撮影した作品もあります。真っ赤に染まるその都市の姿からは、夕日を受けた美しい都市の姿と同時に、恐ろしさも想起させられます」(角)。

付近の壁には「#楽園」「#追放」「#原罪」「#ディストピア」「#ユートピア」というハッシュタグが示されている。旧約聖書の楽園追放という美術史においても重要なモチーフを下敷きに、人が知恵を獲得することで発生する恵みと厄災や、ある場所からの移動を余儀なくされること、そのうえで前に進んでいくことといったイメージが、現代へと変奏されていく。
こうした流れで次に登場するのが、東日本大震災以降、故郷・福島を主題とした作品を多数制作してきた毒山凡太朗の作品だ。本展では広島でのリサーチを経て、フクシマとヒロシマの考察を促す映像インスタレーションを発表する。
「《Stay Home》(2022)は、福島で被災した女性の姿を描いた作品です。帰還困難区域になってしまったので自宅を離れていた人が、ようやく家に帰れるようになりました。そのとき、かつて大好きだった『この☆(ほし)のゆくえ』という曲の楽譜を見つけ、その歌を歌っている様子が映されています。
《Long Way Home》(2022)も同様に、帰還困難区域になってしまった場所にかつて住んでいた女性に焦点を当てた作品。被災した場所やそこに暮らしていた人々の生活のあと先を考えさせられる作品です」(角)。

石内都の出展作も、災害に関連した写真だ。2019年の台風により浸水被害を受けた川崎市市民ミュージアムには石内の作品も収蔵されており、大きなダメージを受けた。これらを被写体とした「The Drowned」シリーズから、新作を交えた展示を展開する。

「もとの作品はかつて川崎市市民ミュージアムでスペースを借りて自らの手でパネル貼りしたという、石内さんにとって思い入れのある作品。それが変わり果てた姿になってしまった。そのこと自体、とてもショックだし、美術館に収蔵されれば安全に保管され続ける、という考えが覆される出来事でした。
石内さんはこれまでにも、被爆者の所持品や自身のお母さんの遺品といった、直視するのはちょっとつらい、とおそらく多くの人が感じるようなもの・ことに向き合ってきました。今回の作品も、浸水被害を受けた自作を実際に見にいき、撮影しました。
作品は汚水に晒され、赤い点に見えるものはカビだそうです。それでもこの作品は汚ならしいものには見えない。記録ではなく、自身がはっとしたところにカメラを向け作品にしている。目をそらすのではなく、対象に向き合う強さに心打たれます」(角)。

このほか展示室B-2、B-3には、広島の歴史や戦争、原爆などに関連する重要なコレクションも多数並ぶ。ウクライナ情勢をはじめ、世界では未だ争いが絶えない。5月には広島でG7サミットの開催が予定されているが、この都市にある現代美術館ならではの展示が、世界各地の世代を超えた人々に共有されることを願って止まない。それと同時に、いわゆるヒロシマの象徴的・画一的イメージにとらわれない、ひねりやずらしがキュレーションの随所で感じられたことも印象的だった。
若手のアーティストも多く暮らし、新しいスペースが誕生するなど、活気のある広島のアートシーン。同館のリニューアルオープンは、この都市にまた新しい風を吹き込むだろう。春から初夏にかけての気持ちのいい季節に、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
関連イベント
https://www.hiroshima-moca.jp/event_list
竹村京「公開修復」
4/22(土)11:00–17:00
5/20(土)11:00–17:00
5/21(日) 11:00–17:00
竹村京によるワークショップ
4/23(日)14:00–16:00
※要事前申込(申込締切:4/6)
新生タイポ・プロジェクトによるトーク
4/29(土)14:00–16:00
コウミユキによるパフォーマンス
5/3(水)13:00–17:00
そのほか、ワークショップやギャラリートークなど開催予定。詳細やお申し込みはウェブサイトよりご確認ください。
福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)
「Tokyo Art Beat」編集長



